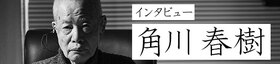――自らのドラッグ体験を書き綴ったベストセラー『スピード』(文春文庫)などで知られるゴンゾ・ジャーナリストの石丸元章。最近は発起人となった異色の掌編小説シリーズ『ヴァイナル文學選書』(東京キララ)も話題となっているが、実はこの秋、脳卒中で倒れ、現在も都内の某有名リハビリ病院に入院しているのだ。そんな中、本人から本メディアに突如届けられたのが以下のテキストである。リハビリにおけるOT(作業療法)の課題として書いたものだというが、そこには発症から今に至る間の真情が吐露されていたのだった――。
サイゾー2018年12月号にも登場した石丸元章。『ヴァイナル文學選書』の第1弾「新宿歌舞伎町篇」に作品を寄せた小説家の海猫沢めろん、ラッパーの漢 a.k.a. GAMI、ジャズメンの菊地成孔と語り合った。(写真/渡部幸和)
親戚の死に方を見ているから、「いつかは自分も脳卒中に倒れるだろう……」くらいには考えていた。ずっと前に死んだ祖父や祖母、それに仲の良かった叔父もまた、ある日突然前触れもなく倒れ、意識を失い、その後何年もチューブにつながれたまま、不気味な人工呼吸器の機械音の中で生き続けるミイラのようになってしまった。
自分の死生観に合わない死に方は嫌だな。40歳を超えてから漠然と考えてきた。
そこへ――突然の脳卒中である。本人が一番驚いた。
いつもの午後いつもの銭湯へ行って湯に浸かろうとすると、じーんと半身が痺れてきた。
「まさか、ちがう病気だといいけど。しかし、早くも来たかもしれない……」
痺れに気づいてすぐ思い当たったのは脳卒中だ。〈気のせいであってくれ〉祈るような気持ちで湯船につかるが、痺れはますます強くなる。祖母や叔父を脳卒中で失ってから読んだ、脳卒中にまつわる記事を思い出す。立ち上がる。めまいはしないが痺れはますます強くなってくる。〈これはまずいな〉。最後の祈りを込めて地下水かけ流しの冷たい水風呂にとぶんと飛び込むと、ジワッ!と痺れが大きく強く広がった。
脳卒中確定だ――! 瞬間自分は立ち上がり、大急ぎでロッカールームへ駆け込む。一刻も早く部屋へ戻って救急車へ電話しなくては。
身体を拭く間もなく衣類を身に着ける。数分のうちに、痺れは強烈なものに変化してきた。額から汗が噴き出る。衣類を身に着けた時には、立っているのがやっとだった。銭湯へ救急車を呼びたくはない。見世物になっちまう。
足を引きずりながら家に帰りつくと、大急ぎで救急車に電話した。全身から汗が吹き出し、額からしたたり落ちる。もう立っていられない。
119のオペレーターに必要事項を伝えたのち、玄関の扉を開け放つ。救急車が来た時に、どこの部屋かすぐわかるように。意識だってどこまで持つかわからないのだから。
救急車を待つ間、心は静かに落ち着いていた。
突然の発病に対してやれることすべてやった――。
満足感すらあった。
仕事の連絡とか、明日のあれとかこれとか、すべては脳卒中という大病の発症に際しては、どうでもいいことだ。これっきり意識を失い、寝たきりになるのかもしれないのだから。
扉を開けた部屋でチェアに腰をかけて救急車を待っている。初秋の風が入ってくる。呆然と天井を見上げる。痛みがないのが幸いだ。人生をゆっくりと反芻できる。
書き手としては、やり残したことが多い一生だった。50歳を過ぎて魂を込めた作品を書くチャンスはいくらでもあったのに、ずるずるしているうちに、こんなことになってしまった。体調を崩して病気がちになった同年代の男友達を「もうすぐ死ぬな」などとからかっていたら、先に自分がこのざまだ。情けない。みんな嗤うだろうな――。
一人息子のことを考える。12歳でパパが脳卒中で死んでしまうのは可哀そうだが、運命だから諦めてくれ。泣くだろうな。まあ離婚したママの実家もあるし、お爺ちゃんたちもいるし、おおよそカネでの苦労はないだろう。家具とか衣類とかシルバーの装飾品類を遺品として整理して渡せなかったのは心残りだが、こうなった以上仕方がない。元気で長生きしてくれ。
そうこうするうち救急車がやってきた。扉を開けておいたから、目星をつけてきた隊員が隊員が、すぐに部屋へ飛び込んでくる。
「脳卒中での救急要請はこちらですか!?」
「そうです」
「ご自分で119番したんですか」
「そうです」
聞かれるままに、発症からの様子を説明する。当然ながら落ち着いて話していられるわけはない。高揚して、酷く吃音していたような気がするし、もしかしたら、すでに脳機能の障害で発声障害が出ていたのかもしれない。
「立てますか?」
「ええ、立てます……」立とうとして半身が効かず、そのまま床に崩れ落ちそうになった。「えっ!……」あわてて支えようとして手を伸ばしたが、片手はだらんと垂れさがってしまい、寸分も動かない。身体の半分が死体となったようで、棚に激しくぶち当たり、大きな音を立てて床にテーブルの物が飛び散った。救急隊員があわてて身体を支えてくれる。
「動かないでください。そのまま椅子に座ってじっとしていて」
隊員は状況を、逐一無線で伝えている。立てないのでストレッチャーが運ばれてくる。男やもめの狭い部屋なので、ストレッチャーはそのままでは入らない。玄関まで自力で歩けるかと聞かれた。歩ける。しかし、またもや現実に愕然とした。片脚がマヒしているのだから、利く方の片脚で跳べばいい――との軽い思い込みは大間違いで、全身のバランスが崩れる。半身がマヒすると、人は片脚でただ立ち上がることすらできなくなる!
力が抜けてしまい、糸の切れた吊り人形のような無様な様で崩れそうになるのを、二人の救急隊員が真っ赤な顔をして支えている。
ストレッチャーに乗ると「これから病院へ向かいます」と告げられた。
「保険証を用意してください」救急隊員が冷静に告げてくる。
「はい」
「それからキャッシュカード。携帯電話は持ちましたか。ご家族など必要な相手に電話してください。簡単な着替えなどはすぐに出ますか。ほかに身分証になるものはありますか」
「パスポートを持っていきます」
矢継ぎ早に救急隊員が話しかけてくる。できる対応はするが無理なこともある。ストレッチャーに横になると、アパート周辺に人が大勢集まっている様子が、目に入ってきた。近所に暮らす連中だ。近くの住民が救急搬送されるのだ――隠そうともせずに、内緒話しをしている老人たち。悪気はないのだろうが、下卑た嫌な視線だ。口に手を当てて笑っているババアがいる。いや本当は笑ってはいないのだが、自分の目にはそのように映っている。
救急車に乗り込み、ほっと一息つく。
ほっとしている場合ではないのだが、好奇の視線に晒されなくて済む、という安堵だ。ここまで最速で進んでるという満足感もあった。
躊躇なく救急車を呼んだのは正しかった。自宅へ戻ったのも正しい。友人への連絡と指示。身分証は持った。戸締り、よし。銭湯で発症したので「下着は新しく身体はきれいだ」と、どうでも良いことへも満足していて、ピーポーピーポーという走行音を他人事のように遠く聴きながら、ぼんやりとこれから先のことを考える――。
いつかは脳卒中で倒れるだろう……。と、考えていて、実際倒れた。そこまではよい。想定通りだ。
しかし、自分がこれまでシミュレーションしていたのはここまでで、倒れてから先のことは、一度も考えたことがなかったのだ。
まったく初めての状況の中で、この先のことを考える――。
「俺も、いよいよここまでか」
意外にもすでに腹はくくられていた。無念だったがこれも運命。じだばたしても仕方がない。救急車に揺られながら、いよいよ半身の感覚が失われていく。隊員に話しかけられても、口から出てくるのは意味をなさない音の羅列で、いつの間にか、もう言葉すら話せなくなっている。
脳卒中で倒れたのち、意識を失ったまま数年以上も生命維持装置につながれて生き続けた祖父母や叔父のようにはなりたくなかった。祖父母は戦争経験者でもあり、年金に加えて軍人恩給が支給されて――植物状態だろうが何だろうが生きているだけで黒字経営になる。と、あけすけな話を聞かされていたのも、自分がその状況を嫌悪してきた理由だ。
いつ死ぬかは自分の意思で――。
これはもうずっと前から決めている強く明確な自分の死生観である。死ぬときは拳銃自殺で。
いつかはわからないが、自分が自分であるうちに、作家らしく、自分の人生に自分自身で「。」打って自分で死にたい。〈自分が自分である〉ということをどう定義するかはそれぞれだが、要するに肉体的にも知能的にも、これが自分だ!と自分自身が自信を持って言える自分。
拳銃自殺は格好が良く、いかにも自分好みだ。川端康成はガスホースを咥え、三島由紀夫は切腹をした。太宰は入水だ。海外に目をやると、ヘミングウェイが猟銃自殺。ハンター・S・トンプソンが拳銃自殺だが、日本ではまだ、拳銃自殺した作家はいないはずだ。
しかし問題もあった。いつ死ぬかもわからないのに拳銃を手に入れて、見つかりでもしたら刑務所行きだ。第一どこで手に入れる。「今や日本でも、インターネットで拳銃くらい簡単に手に入る」という人もいるが、実際には難しい。拳銃は薬物などと違って、その辺で簡単に買えるものではないのだ。値段だって高いだろう。仮に拳銃が手に入るとして、それが安物のトカレフのようなまがい物でいいのだろうか。死ぬには死ぬのにふさわしい、きちんとしたアメリカ製の357マグナムのような立派な拳銃が必要ではないか。
じつのところ、それが最大の自分の死の悩みだったし、身近であっても良いはずの死が、どこか空想の向こうにある、いつかの遠い出来事であった理由だったのだが……。
偶然にもこの夏、タイミングよく、すべてを解決できる方法を見つけていたのだった。
すべてはグアムへ飛行機で行けば解決する。グアムの先住民族はチャモロ族といって、観光客の御用聞きのようなことを仕事にしている者が多い。持ってこいと言って小遣いを渡せば拳銃は選び放題。詳しい説明をしなくても、米領グアムで拳銃を手に入れることが容易であることは、誰でも想像できるだろう。帰りの席はいらないのに、往復分のエアーチケットを買わねばならないのは癪だが、それは迷惑料として――3泊5日のツアー料金が15万円。拳銃が5万円。最後の一晩のバカ騒ぎが10万円。それくらいなら誰かが貸してくれるだろう。向こうでの火葬に関する支払いは、俺の知ったこっちゃない。もう死んでるんだから。お別れ会をやってほしいとか、忘れないでほしいという希望は一つもない。12歳の息子には気の毒だが諦めてもらうしかない。それがわれわれの別れ方なんだね。少しだけ壮絶だね、君の人生。楽しく長生きしろよ。
救急車の天井を眺めながら、完全に達観していていることに驚いていた。何の迷いもない。恐怖も後悔もなく悲痛な叫びもなく、「ここから先、自分が自分でなくなったら死のう」と、泰然と大きく、世俗を離れた悟りのような心境に到達していた――。そして……それから今日で51日。集中治療室を3日で出た自分は、見る見る回復して急性期病院を約3週間で退院。そして現在は回復期のリハビリ病院へ入院しているわけですが、本当に元気になって、たぶんもうすぐ退院。もう一度世の中に戻り、そして、もう一度作家として勝負するという人生へ航路を切り戻している。
こうなった以上、これも運命だ。俺は往生した!という開き直りを、有意義な覚悟に変え、今は全力で仕事をして生き抜いてやるーーと、そう気持ちを新たに意気込んでいるのはいいんだけど、あの時の泰然大悟の死を決めた心情は、この50日の間にどこかへ行ってしまって、人気者になりたいとか売れたいとか、若い子と恋愛がしたいとか、ちまちました悩み事に追い立てられながら、またいつもの生活を始めようとしているのです。
『ヴァイナル文學選書』の第1弾「新宿歌舞伎町篇」では、石丸は『聖パウラ』という作品を書いた。
石丸元章(いしまる・げんしょう)
1965年生まれ。作家、ゴンゾ・ジャーナリスト。96年、自身の麻薬体験を綴った私小説 的ノンフィクション『スピード』(文春文庫)を出版し、ベストセラーに。ほかに『平壌ハイ』(同)、『DEEPS』(双葉文庫)、『覚醒剤と妄想 ASKAの見た夢』(コア新書)などの著書がある。掌編小説シリーズ『ヴァイナル文學選書』(東京キララ社)の発起人でもある。