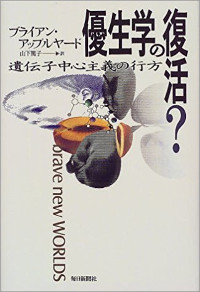ナチスドイツの政策にも影響を与えた“優生学”。学術史上最大のタブーとされる学問であるが、その成り立ちはいかなるものだったのだろうか? 進化論や遺伝学などの論点から紐解いてみたい。
『優生学の復活?―遺伝子中心主義の行方』(毎日新聞社)
「遺伝、見た目、教育に関わる『不愉快な現実』」
そんな刺激的な帯の文句で売り出した、『言ってはいけない 残酷すぎる真実』(新潮新書)は、電子版を合わせると50万部というベストセラーとなり、2017年の新書大賞を受賞した。同書をかいつまんで説明すれば、人間の知能、性格、さらには成長してどのような疾患にかかるかといった点まで、かなりの部分が遺伝によって決まっているという。従って、「人間は平等だ」とか「努力は報われる」といった言葉は、幻想に過ぎないというのだ。本書の第一章「遺伝にまつわる語られざるタブー」には、次のように書かれている。
「一般知能はIQ(知能指数)によって数値化できるから、一卵性双生児と二卵性双生児を比較したり、養子に出された一卵性双生児を追跡することで、その遺伝率をかなり正確に計測できる。こうした学問を行動遺伝学というが、結論だけを先にいうならば、論理的推論能力の遺伝率は68%、一般知能(IQ)の遺伝率は77%だ。これは、知能のちがい(頭の良し悪し)の7~8割は遺伝で説明できることを示している。
どれほど努力しても逆上がりのできない子どもはいるし、訓練によって音痴が矯正できないこともある。それと同じように、どんなに頑張っても勉強できない子どももいる。だが現在の学校教育はそのような子どもの存在を認めないから、不登校や学級崩壊などの現象が多発するのは当たり前なのだ」
人間の能力の大部分は遺伝で決まっており、教育でできることが限られているという主張は物議を醸しそうだが、著者の橘玲氏に直接寄せられた反応の中には、批判的なものはほとんどなかったという。橘氏が話す。
「この本は小さい子どもを子育てしている母親にも結構読まれたのですが、『この本を読んで救われた』という声が、かなり多かったんです。考えてみるとそれも当然で、子どもの能力が低いのは遺伝ではなく環境のせいだとなれば、悪いのは親だ、と責められるわけです。しかし遺伝の影響が大きいのなら、親のできることには限りがある。『自分の育て方のせいじゃないんだ』とわかって、肩の荷が下りたというのです」
今、世間では広く幼児教育の大切さが叫ばれ、子どもの学力は親の力で伸びるといった本もあふれているが、実はそうした本で苦しめられていたのは、ほかならぬ親たちであったのだ。
『言ってはいけない』の文中には、エビデンスとして東西のさまざまな専門書に書かれた学術的な研究が挙げられ、その出典は同書の巻末に参考文献として示されている。安藤寿康『心はどのように遺伝するか』(講談社ブルーバックス)、A・R・ジェンセン『IQの遺伝と教育』(黎明書房)、リチャード・ドーキンス『利己的な遺伝子』(紀伊國屋書店)といったそれらの本は、進化心理学や社会生物学といった学問領域のものが多い。人間の心理や生物社会行動を生物学的に解き明かすそれらの学問は、特に1980年以降、リベラル陣営からある学問と同一であるとレッテル貼りされることから、必死で抵抗してきた歴史がある。その学問こそが、第二次世界大戦以降タブー視されてきた、“優生学”という領域である。
人気記事ランキング
新・ニッポンの論点
- “分断の時代”に考える20年代の【共産主義と資本・自由主義】
- ロシアが社会主義国に見える理由
- 友好国だからこそぼったくる!「トランプ帝国主義」
- 全国紙も報じた終末論【2025年7月人類滅亡説】のトリセツ
- 世代を超えたカリスマ「SEEDA」の【アップデート&処世術】
- 『GQuuuuuuX』で変わる!? ガンダムの【IPビジネス新戦略】
- 教えて! 大﨑洋さん!! 逆風での船出「大阪万博」の愉しみ方
- パレスチナのジェノサイドと【日本の難民問題】の深層にあるもの
- さらば?芸能界のドン、【バーニング周防郁雄社長という聖域】
- [週刊誌記者匿名座談会]憶測と中傷び交う中居・フジ問題の論点
NEWS SOURCE
インタビュー
- 【沖 侑果】上京して間もなく1年、目標は「新しい友達を作る」!
- 【Miyauchi】彗星のごとく現れた〝今が大事〟な川崎の超スーパースター
- 【原つむぎ】グラビア界の至宝が、こだわりのボディメイクで作り上げた圧巻の肉体美
- 【中村正人×堤幸彦】夢を実現させる場所「渋谷 ドリカム シアター」プロジェクトが描く未来予想図
連載
- 【マルサの女】名取くるみ
- 【笹 公人×江森康之】念力事報
- 【ドクター苫米地】僕たちは洗脳されてるんですか?
- 【丸屋九兵衛】バンギン・ホモ・サピエンス
- 【井川意高】天上夜想曲
- 【神保哲生×宮台真司】マル激 TALK ON DEMAND
- 【萱野稔人】超・人間学
- 【韮原祐介】匠たちの育成哲学
- 【辛酸なめ子】佳子様偏愛採取録
- 【AmamiyaMaako】スタジオはいります
- 【Lee Seou】八面玲瓏として輝く物言う花
- 【町山智浩】映画でわかるアメリカがわかる
- 【雪村花鈴&山田かな】CYZOデジタル写真集シリーズ
- 【花くまゆうさく】カストリ漫報