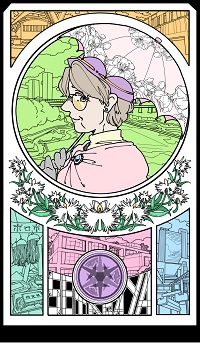東京都23区――。この言葉を聞いた時、ある人はただの日常を、またある人は一種の羨望を感じるかもしれない。北区赤羽出身者はどうだろう? 稀代のコラムニストが送る、お後がよろしくない(かもしれない)、23区の小噺。
(絵/ジダオ)
「トロフィーワイフ」という言葉がある。功成り名遂げた男が、自らの人生の成功の証として手に入れる賞品のような妻、といったほどの意味だ。
駒沢競技場を望むオープンカフェで、談笑するマダムたちのいずれ劣らぬこれみよがしな美貌を眺めながら、静子は昔、なにかの本で読んだトロフィーワイフという言葉を思い浮かべている。万事にカネのかかった女たち。カネの出どころは本人ではない。アタマからつま先までを積算して合計すれば、100万円はくだらないはずのその彼女たちの服飾関連出費を鷹揚に支出しているのは、10歳以上は年齢が上の夫ということになっている。
日曜日の午後、駒沢公園前のカフェに集うマダムたちは、自分たちが買い取られた資産であり、自分の脚で歩く期間限定の不動産である旨を強く自覚している。だからこそ、個々のトロフィーワイフは、自身に投入された金額の多寡を、端数の10円の単位に至るまで頑強に記憶しているのだ。
その点、私は、身に着けているもののすべてを、一から十まで、自腹で買い揃えている。そういう意味で自分はトロフィーではない。
「どちらかといえば」
と、静子は考える。
「あたしはトラップなのかもしれない」
スマホが鳴る。通話の着信音ではない。LINEの通知を知らせる幽かな擦過音だ。その曇りガラスを引っ掻くような神経に触る音色を、彼女は、メッセージを伝える効果音に採用している。
「いま渋谷。あと30分でそっちに着くよ」
娘からLINEのメッセージが届くようになったのは、2カ月ほど前からのことだ。
それまで、静子は、彩美がスマホを持っていることさえ知らずに過ごしていた。今年の4月、福島の母親のもとにもう5年も預けっぱなしにしている彩美が、突然電話をかけてよこしたのは、中学に入学して、自分用のスマホを手に入れたからだった。
「おかあさん。あたし。わかる?」
彩美は屈託なく笑っている。まるで天使みたいに。5年も会っていないのに。小学2年生の夏休みに実家に置き去りにして、以来、ハガキ一枚、電話一本よこしていない母親を、このコは、まるで恨んでいないように見える。本当だろうか。
「ねえ。おかあさん。あたしのLINEに登録してよ」
以来、彩美は、週に1度か2度、近況を短い文章とスタンプで知らせてくるようになった。
「席替えがあったよ」
「隣の席のオトコ最悪。やくざものだよ」
「部活やめたよ。面白くないからね」
「ねえ、英語って必要? 誰に使うの?」
「カズが金髪にして呼び出しくらって金髪のボウズになって、で、3日で色がぬけた。超ウケる」
静子は、メッセージを受け取る度に、5文字以内の簡単な返事を書く。文字の入力が得意でないということもあるが、本当のところ、どんなふうに返事をして良いのやら、毎回見当がつかないのだ。
人気記事ランキング
新・ニッポンの論点
- “分断の時代”に考える20年代の【共産主義と資本・自由主義】
- ロシアが社会主義国に見える理由
- 友好国だからこそぼったくる!「トランプ帝国主義」
- 全国紙も報じた終末論【2025年7月人類滅亡説】のトリセツ
- 世代を超えたカリスマ「SEEDA」の【アップデート&処世術】
- 『GQuuuuuuX』で変わる!? ガンダムの【IPビジネス新戦略】
- 教えて! 大﨑洋さん!! 逆風での船出「大阪万博」の愉しみ方
- パレスチナのジェノサイドと【日本の難民問題】の深層にあるもの
- さらば?芸能界のドン、【バーニング周防郁雄社長という聖域】
- [週刊誌記者匿名座談会]憶測と中傷び交う中居・フジ問題の論点
NEWS SOURCE
インタビュー
- 【沖 侑果】上京して間もなく1年、目標は「新しい友達を作る」!
- 【Miyauchi】彗星のごとく現れた〝今が大事〟な川崎の超スーパースター
- 【原つむぎ】グラビア界の至宝が、こだわりのボディメイクで作り上げた圧巻の肉体美
- 【中村正人×堤幸彦】夢を実現させる場所「渋谷 ドリカム シアター」プロジェクトが描く未来予想図
連載
- 【マルサの女】名取くるみ
- 【笹 公人×江森康之】念力事報
- 【ドクター苫米地】僕たちは洗脳されてるんですか?
- 【丸屋九兵衛】バンギン・ホモ・サピエンス
- 【井川意高】天上夜想曲
- 【神保哲生×宮台真司】マル激 TALK ON DEMAND
- 【萱野稔人】超・人間学
- 【韮原祐介】匠たちの育成哲学
- 【辛酸なめ子】佳子様偏愛採取録
- 【AmamiyaMaako】スタジオはいります
- 【Lee Seou】八面玲瓏として輝く物言う花
- 【町山智浩】映画でわかるアメリカがわかる
- 【雪村花鈴&山田かな】CYZOデジタル写真集シリーズ
- 【花くまゆうさく】カストリ漫報