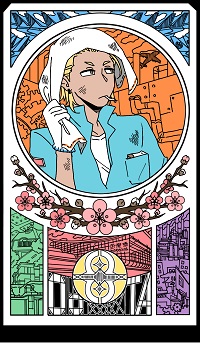東京都23区――。この言葉を聞いた時、ある人はただの日常を、またある人は一種の羨望を感じるかもしれない。北区赤羽出身者はどうだろう? 稀代のコラムニストが送る、お後がよろしくない(かもしれない)、23区の小噺。
(絵/ジダオ)
「颯太?」
と、いきなり背中を叩かれて、柳田颯太は後ろを振り返った。
「やっぱり颯太だ」
声の主はあゆみだった。
「あんたなんのつもり?」
「なんのって、なにがだよ」
「その髪よ。きったない金髪。どうしたのそれ。何かの罰ゲーム? それともグレたわけ? いいトシして今さらそこいらへんの中坊みたいに」
「なんでもないよ」
「へー。なんでもなくてある日髪の毛の色がガイジンみたいな金髪になるんだ」
「悪いけど急いでるんだ」
「急いでるって、もしかして映画のオーディションでも受けるつもり? ハリウッドとかの。それで金髪に変装してるわけ?」
「うるせえな」
「うるせえなじゃないでしょ。一体どういうつもりなのよこれは? こんなバカなチンピラみたいなアタマで世間を歩いて。本当のバカになったの?」
あゆみは幼なじみだ。というよりも、家族に近いかもしれない。姉なのか妹なのかは微妙なところだが、子ども時代の長い時間を共に過ごした間柄だ。
「あんた、勤め先にはマジメに通ってるの?」
「うるせえな」
「うるせえなって、どこのガキよ。もう少し人間らしい返事できないの?」
「ほっといてくれよ」
「だから質問に答えなさいよ。仕事はどうしたの?アタマは何事? 人生投げてんじゃないの?」
「おまえこそアタマおかしいんじゃないか?」
「どうなのよ。仕事は辞めてないんでしょうね」
「辞めてないよ。毎日真面目に出勤してるよ」
「それは良かった。で、勉強はしてる? ちゃんと食事は摂ってる?」
「お前はオレのオフクロか?」
「あんたのお母さんのこと言ってるんなら、あのヒトはもう帰って来ないよ。きれいな人だったけど、人間が弱かった。あたしは、あんたがその弱さを受け継いでるんじゃないかって心配してるんだよ。わかってる? あんたヤケになってない?」
「うるせえな」
「ほら、やっぱり大切なアタマを金髪なんかにしてるからボキャブラリーが激減してる。きっと知能指数だって半分ぐらいになってるよ」
「メシはちゃんと食ってるし、仕事もしてる。アタマは気分転換。勉強は辞めた。以上報告終わり。満足したか?」
「ちょっと。勉強辞めたっていうのは、どういうこと? あんた自分の状況わかってるの?」
「余計なお世話だよ」
「あんたは余計なお世話が必要な人間なんだよ。わかってるの? で、勉強やめたって何よ。一体どういうつもりなの?」
あゆみが颯太の現状にしつこく介入したがるのは、3年前に母親を亡くした颯太が、19歳で自活を余儀なくされている境遇をよく知っていたからだ。
人気記事ランキング
新・ニッポンの論点
- “分断の時代”に考える20年代の【共産主義と資本・自由主義】
- ロシアが社会主義国に見える理由
- 友好国だからこそぼったくる!「トランプ帝国主義」
- 全国紙も報じた終末論【2025年7月人類滅亡説】のトリセツ
- 世代を超えたカリスマ「SEEDA」の【アップデート&処世術】
- 『GQuuuuuuX』で変わる!? ガンダムの【IPビジネス新戦略】
- 教えて! 大﨑洋さん!! 逆風での船出「大阪万博」の愉しみ方
- パレスチナのジェノサイドと【日本の難民問題】の深層にあるもの
- さらば?芸能界のドン、【バーニング周防郁雄社長という聖域】
- [週刊誌記者匿名座談会]憶測と中傷び交う中居・フジ問題の論点
NEWS SOURCE
インタビュー
- 【沖 侑果】上京して間もなく1年、目標は「新しい友達を作る」!
- 【Miyauchi】彗星のごとく現れた〝今が大事〟な川崎の超スーパースター
- 【原つむぎ】グラビア界の至宝が、こだわりのボディメイクで作り上げた圧巻の肉体美
- 【中村正人×堤幸彦】夢を実現させる場所「渋谷 ドリカム シアター」プロジェクトが描く未来予想図
連載
- 【マルサの女】名取くるみ
- 【笹 公人×江森康之】念力事報
- 【ドクター苫米地】僕たちは洗脳されてるんですか?
- 【丸屋九兵衛】バンギン・ホモ・サピエンス
- 【井川意高】天上夜想曲
- 【神保哲生×宮台真司】マル激 TALK ON DEMAND
- 【萱野稔人】超・人間学
- 【韮原祐介】匠たちの育成哲学
- 【辛酸なめ子】佳子様偏愛採取録
- 【AmamiyaMaako】スタジオはいります
- 【Lee Seou】八面玲瓏として輝く物言う花
- 【町山智浩】映画でわかるアメリカがわかる
- 【雪村花鈴&山田かな】CYZOデジタル写真集シリーズ
- 【花くまゆうさく】カストリ漫報