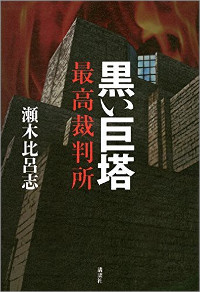――ビデオジャーナリストと社会学者が紡ぐ、ネットの新境地
[今月のゲスト]
瀬木比呂志[元裁判官・明治大学法科大学院教授]
『黒い巨塔 最高裁判所』(講談社)
以前から、裁判官による不可解な判決は少なからずあったが、ここに来て特におかしな判決が多くなっているように思える。元裁判官の瀬木比呂志氏によれば、裁判官による政治へのおもねりや自身の保身という基本的な習性は変わっていないが、近年は裁判官の劣化が激しくなっているという。中でも国策をめぐる裁判では、それが顕著だというが……。
神保 今回は司法の問題を取り上げます。司法というと、警察や検察の人質司法が問題になることが多いですが、今回は裁判所の責任を考えたいと思います。日本の司法がなかなか前時代的な人質司法を脱せないのは、もちろん警察や検察の問題もありますが、実際は裁判所に最終的な責任があると言っても過言ではないと思います。検察の長期勾留を認める令状を出しているのも裁判所だし、拷問まがいの取り調べによって出てきた自白の任意性を認めているのも裁判所です。人質司法の問題点は根底に裁判所がそれを認めているという点がありますが、その責任はほとんど追及されてきませんでした。
宮台 基本的に社会は“いいとこ取り”ができません。法実務の世界においてもそう。裁判所の数、検察官の数、弁護士の数、検察の行政的営み全体、検察官と政治の関係、例えば官房長官の関わりなど、すべてが噛み合っているので、どこか一部分だけ変えることが難しい。そうだとしても、こうした全体性に目を配る立場があるとすれば、やはり裁判所しかないだろうと言わざるを得ません。
神保 我々がこれまで扱ってきた裁判の判決を見ただけでも、首を傾げたくなるものが多くあり、明らかに日本の裁判所は問題を抱えていると思います。沖縄の辺野古埋め立て訴訟や、美濃加茂市長収賄事件裁判の高裁判決(藤井浩人市長の逆転有罪)もそうです。和歌山のカレー事件でも、唯一の物証に疑義が呈されているにもかかわらず、裁判所は再審請求を認めようとしません。このような判断が出る背景には、なんらかの構造的な問題があるのではと考え、今回のテーマを設定しました。
ゲストは3年前にもご登場いただきました、元裁判官で明治大学法科大学院教授の瀬木比呂志さんです。前回は『絶望の裁判所』(講談社現代新書)をお出しになったあと、「誰も知らない裁判所の悲しい実態」と題してお話を伺いました。昨年10月には『黒い巨塔 最高裁判所』(講談社)という小説を出されました。実例もたくさんお持ちなのに、あえて小説という形を取られたのはなぜでしょうか?
瀬木 大きな理由として、既刊2冊の新書は客観的な事実、推論ということで縛りがかなり強く、裁判所の実際の雰囲気、最高裁のリアルな権力構造、官僚裁判官たちの人間像等が描けなかったことがあります。裁判官も人間なので、多くは良心も持っており、自己承認欲求もある。では、そこにどんな力学があって、どうしてこういうふうになってしまうのか――ということを描くには、ノンフィクションでは限界があったんです。
神保 なるほど。最初に総論的なところで、ここ数年の日本の裁判所を、どう評価されていますか?
瀬木 もともと構造的な問題があり、それがだんだん大きくなってきたところで、2000年代の司法制度改革がありました。しかし、これは裁判所の権益確保のために利用されるなど、あまりいい改革にはならなかった。法テラスのように成功した部分もありますが、全体として見ると、司法制度改革は失敗、むしろ悪用されたと言わざるを得ません。
その中で、裁判所はもっぱら権力に擦り寄っていくようになり、個々の裁判官が受ける圧迫も大きくなっていきました。今や、本来あるべき権力チェック機構ではなく、権力補完機構になっているように見えます。同じく権力をチェックする存在であるべきメディアも、マスであるほどそういう傾向が強くなっている。この構造を破らなければ、おそらく新しい方向性は見えてこないでしょう。
宮台 そこには「誰のために何をしているのか」という動機付け問題が控えていると感じます。米国ではトランプ大統領について「誰のために何をしているのか」が疑われ、日本でも天下り問題が再燃して霞が関官僚が「誰のために何をしているのか」が疑われている。裁判官についても「誰のために何をしているのか」が疑わしい。どこもかしこも、国益のためや国民益のために仕事をする代わりに、一族のため・一省庁のため・一身の保身のために仕事をしているのではないか……と。これは小手先の制度変更では克服できません。司法問題に留まらず、各国の社会全域に広がる大問題だからです。説明します。
福祉国家行政時代のような再配分が不可能になった理由として、財政難が挙げられます。でも僕の考えではそれに留まらない。新自由主義的志向の背景には、「どこの馬の骨ともわからぬ『国民』のために」自分のカネを再配分するなんてあり得ないという感覚が控えています。それにシンクロして、先進国はどこでも戦争に関して「どこの馬の骨ともわからぬ『国民』のために」命を投げ出すなどあり得ないとの感覚が普通になっています。同じ論理で「どこの馬の骨ともわからぬ『国民』のために」働くなどあり得ないという感覚が、国を問わず広がっています。抽象的に言えば、各国は動機付けの調達に問題を抱えるようになったのです。ちなみにこれは1950年代に社会学者パーソンズが予告していた問題です。
日本の司法が求めるものは正義か、それとも自己承認欲求か?
神保 誰でも多少は保身や出世を考えるでしょうが、それによって本来、裁判官として最優先されなければならない正義が歪められてしまっているということでしょうか?
瀬木 それは昔からあると思います。根本にあるのは、出世というより、自己承認欲求。本来なら、よい判決を出して、それがきちんと評価されて、承認されるというのが正しい形ですが、そうではなく、異常な形のヒエラルキーの中で認められることが目的になってしまっている。根本が歪んでいるんです。そして裁判所は、メディアや官僚の世界より、さらに内側に非常に閉じています。つまり裁判所は、上から裁判する立場でしか外と接しないので、より閉じた構造になるんです。これが非常に難しい。
また日本特有の現象として、建前と本音の乖離という問題があります。アメリカ人だったら、「偉くなりたい」「金を儲けたい」という言葉が出てくるので、それを自分でも自覚できるし、周りも批判できる。しかし日本の場合は建前ばかりが前に出て、自分の中にあるドロドロしたものは何か、ということがまったく詰められていない。そのなかで「正義」などと言っても、鶴見俊輔の言う“フケ”のようなもので、ボロボロと落ちて、残るのは非常に露骨な上昇志向、権力欲でしかない。すべてがそうとは言いませんが、そういう人たちばかりが上に行く。組織としての問題が非常に大きいのです。
神保 瀬木さんのご著書を参考に、「異常な判決が出る背景」を私なりにまとめてみました。過不足あればご指摘いただきたいのですが、「統治と支配の担い手意識」「仲間意識」「ねじれたプライド」「権力へのおもねり」「ポピュリズム」としています。
瀬木 事務総局周辺で出世をしたい人たち、つまり最高裁判所の行政、司法行政をやっている人たちの特徴は、これでほぼまとまっているという感じです。
一方で、ごく普通の裁判官がどうかと言えば、ここまではっきりしたものはありません。せいぜい、「自分は一生懸命頑張っています」というような意識で、全体を見渡す視点などまったくない。僕自身、全体の構造を正しくとらえられるようになったのは、辞めて自分でさまざまなことを調べてからです。
神保 いわゆる“ムラ”ですね。瀬木さんでさえ「全体が見えなかった」と言われるんだから、見える人はいないのでしょう。
では、個別の問題を見てみましょう。瀬木さんが『黒い巨塔』の中でも扱っていた原発について、再稼働を差し止める決定が3回ほどありました。樋口英明裁判長が2度、山本善彦裁判長が1度、原発再稼働の差し止めを認めています。もっとも、樋口裁判長の決定は、その後、覆されてしまいました。
瀬木 同じ地裁で取り消されていますね。樋口さんが転勤された後、3名の裁判官が入ってきて、それが全員、最高裁事務総局勤務経験者でした。
神保 この3人は、樋口さんの仮処分を取り消すために送り込まれたと考えていいですか?
瀬木 その通りです。実は、原発訴訟においては、昔からいざ判決という段階になると、いわゆるエリート的官僚裁判官が入ってくるという人事がある。今回は非常に露骨で、樋口さんは名古屋家裁に異動になった。これは明らかな左遷で、少なくとも内部の人間には「あの裁判が原因で、こうなったんだ」ということがわかる。
神保 『黒い巨塔』を読むと、裁判官の人事というのは、最高裁の長官と事務総長が事実上、牛耳っているという印象を受けました。
瀬木 そこまで極端な話ではないにしても、最高裁長官は、相当に人事を左右することができます。人事局長は、最高裁長官、事務総長より権力がずっと小さいから、圧力をかければ簡単なこと。それを止めるには、ある意味で彼らの自制に期待するしかない。まあ、人事局長の人事自体、上の意向を読んでやっているわけで。
神保 逆に、判決をひっくり返した裁判官は、原発の再稼働に対して、安全基準も避難も問題ないというようなことを平気で書いています。特に避難については、原子力規制委員会も判断はしないとしているので、裁判所が独自に安全性を判断したことになります。裁判官たちは、どういうマインドで、このような判決を書いているのでしょうか?
瀬木 これは個々の裁判官がどうという問題ではなく、日本の裁判官の多数派なら、こういう判決になります。原発事故の後、司法研修所で2回、協議を行っており、入手した資料によれば、2回目には「仮処分は消極」という方向性が出ている。これを見ると、多数派の裁判官はそういう方向なのだ、ということが読み取れます。
神保 どんな理屈で、そうなっているのでしょうか?
瀬木 山本七平が言う「空気」のようなものです。原発事故の直後は空気が揺らぎ、裁判所の過去の判決も批判されるし、積極的に判断しようかなという空気になった。しかし、それからまた1年もたつと、「伊方原発訴訟の枠組みに戻れ」となり、皆それに従うんです。
神保 判決を書くときに、「自分が書いた判決で再稼働された原発に、もしものことがあったら」ということは考えないのでしょうか?
瀬木 考えるべきだし、まともな裁判官だったら考えて当然でしょう。しかし、樋口仮処分の取消決定など、事故が起こり得ることを既定の事実として、なおそういう判断をしている。これを見ると、よほど突出した強い意識や知性の持ち主、あるいは東京から離れて事態をある程度クールに見られる人でなければ、まともさが保てないという感じです。
宮台 僕は大学とは別にさまざまな領域で教育に関わる活動をしてきて、思うことがあります。僕が通った60年代後半の小学校には、団地の子・商店街の子・農家の子・ヤクザの子・医者の子、いろんな子がいた。それから10年たった70年代後半、団地の学校に通うのは団地の子だけになり、80年代に入ると前半は校内暴力、後半はイジメが噴き出します。この80年代後半、管理者責任の追及を恐れる行政による、屋上ロックアウト・校庭ロックアウト・公園の箱ブランコ撤去などが全国で一挙に進みました。
80年代後半に大学教員になったときに僕が思ったのは、昔に比べて同調圧力の縛りがきつくなったなということ。本音の共有つまり共通前提を信頼できた頃は、法律や条令などの決まりは建前に過ぎず、いろんなことが自由にできたのに、共通前提を信頼できなくなったら、一挙に法律や条令に従えという圧力が増しました。だから、80年代後半以降に小学生になった世代と、以前の世代とでは、社会にはいろんな奴がいるという理解や寛容さが違うように僕は感じてきました。
神保 その理解があれば、本当はバランスが取れるはずです。
宮台 そう。「何事もやり過ぎは駄目」という方向で相殺勘定みたいな動きが起こり得たのだけれど、それが起こらなくなって、過剰に一方向に進みやすくなった印象がありますね。
神保 原発問題の根底にある、「何がなんでも原発を続けていく」という強い意思は、どこから出てくるのでしょうか? 一応は原発ゼロを目指した民主党政権下でさえ、裁判所は必ずしも原発を止めるという方向には向かわなかった。政権が代わって、一時的とはいえ原発推進が国策でなくなったにもかかわらず、裁判所に対しては原発推進の「空気」が有効だったということを、我々はどう理解すればいいのでしょうか?
瀬木 裁判所のみならず、多くの人が、やはり民主党政権は長続きしないと思っていたでしょう。当時も、自民党がまた復帰するということを前提にしていたのは間違いないと思います。「統治と支配」の根幹にあることには触れない――エリートは意識的に、普通の裁判官はもう少し無意識的にそうなっています。換言すれば、「社会的価値にかかわる事案」については全体に消極です。
宮台 瀬木さんが引用した山本七平『「空気」の研究』(文春文庫)のフォローアップ・リサーチで重要なのは、社会心理学者の山岸俊男氏のものです。いわく、日本では「公」の概念が、内集団(所属集団)のための自己犠牲を意味しますが、近代社会の「公」は、内集団も外集団(非所属集団)も含めたすべてがそこに含まれる包括集団にコミットすることを意味します。要は市民社会のルールを大切にすることです。
日本は、江戸の歴史を背景に、内集団から出る営みが例外的になり、集団から外れた存在を守る社会的装置がないから、内集団のためにすべてを捧げるのが生存戦略として合理的になる。自分の座席を失わないことにすべてを懸けるという意味で、日本人が世界一自己中心的。集団主義とは自己中心主義の別名だと。原発事故以降、山岸仮説の妥当性が実証されました。自分の座席の保全に汲々とするクズが集まったのが、ウヨ豚や糞リベです。
神保 そんなことをすれば中枢から排除されてしまう、ということですね。例えば前出の樋口裁判官も、裁判所では特異な存在なのでしょうか?
瀬木 浮いた存在ではあると思います。大学に移ってこの5年間で思ったのは、日本ではなぜただ真の自由主義者であることがこんなに大変なのか、ということです。今の、包括集団がないという問題ですね。裁判所でも思い切った判決を書くと、一遍に風圧がかかることになります。その中で、樋口さんなどはあえて、その道を選んだ。最初の判決は、表現など「ここまで書くか」と少し思いましたが、仮処分は短いけれど論理がベターになっていた。その後、山本(善彦)さんがさらにそれらを深めるようなことを書いており、全体として非常に評価すべきだと思います。
形式論理で判決を出す日本司法界の構造
神保 次に直近のものとして、翁長雄志知事による沖縄県辺野古基地の埋め立て承認取り消しをめぐる訴訟について伺います。承認取り消しは違法だという判決が出て、実際に工事が再開されているわけですが、ここでも高度な政治的問題、今回のような安保、米軍にかかわるものについては、裁判所は政府の方針をひっくり返すようなことはしない、という明確な意思表示がありました。憲法学者の木村草太さんによれば、翁長さんの行為を違法にするためにはこれしかない、という形で書かれた、かなり無理のある判決だということでしたが、瀬木さんは、どうご覧になりますか?
瀬木 この判決については最高裁は新しいことを言っておらず、高裁の判断に裁判所の姿勢がほぼ出ていると思います。その特徴は「辺野古が唯一の選択肢」という国の意向を前提とし、県の主張には耳を傾けていないことです。県の主張を正面から判断せず、わずかな審理期間で「前知事の決定が違法とは言えない以上、その取消は違法だ」とした。取消という新しい行政処分の当否が問題になっているのだから、その正当性について検討するのが行政訴訟のあり方として当然なのに、それをまったくしていない。結論ありきの方向性が極端に強い判決で、非常に驚きました。
神保 公害訴訟など国賠に関わるような裁判でも、裁判所は国に完全に寄り添っているケースが多いように思います。裁判所は独立した三権分立のひとつですよね?
瀬木 要するに、「統治と支配」の根幹に触れるものは最初から国寄りなんです。ごく小さい国賠であれば、裁判官により原告が勝つこともあるので、すべての行政訴訟がということではなく、やはり「統治と支配」の根幹にかかわるかどうかがポイントになっている。特に最高裁は、そこにかかわるほど、国寄りの姿勢が強くなります。
神保 自身が統治と支配の担い手になっているのであれば、これはもはや、裁判所ではないですよね。
瀬木 そうなんです。戦後の裁判所の歴史を見ていくと、だんだんとそういう意識が強くなってきて、権力から一定程度離れて客観的にチェックするという方向性が失われてきています。今回の判決理由を見ても、本当に形式論理でしかない。
宮台 文芸評論家の江藤淳さんが長い間「アメリカの影」を語ってきました。日本の左翼は9条護憲主義だが、これはアメリカの核の傘が存在しなければとても主張できないものです。当初はそれを信じる人が多数だとはいえず、共産党も9条反対を唱えていました。なのに「アメリカの武力におんぶに抱っこの9条護憲」が途中から忘却される。吉田茂と白洲次郎による「戦後復興に傾注するための戦略的対米従属」も途中から忘却される。結果「アメリカの影」はどんどん濃くなるばかり。今や右も左もアメリカに這いつくばった状態です。僕は過去30年近く「重武装・対米中立」を唱えてきたけど、実際のところ「対米ケツナメ路線」を捨てた途端、右も左もすべて空っぽになって何も回らなくなるのが、今の状況です。
神保 戦後積み上げられてきたものを今さらイチ裁判官がひっくり返せない、という気持ちはわからなくはないですが、なぜ、それができないのでしょうか? 裁判所にできることはたくさんあるように感じます。
瀬木 いろいろな問題があります。裁判官の意識の問題として、それなりに切り込んだ判断をするためには、その人なりのビジョンがないとできない。しかし、そういうものを持っている裁判官が一体どれだけいるか。また、そういうものを持っていたとしても、それが発揮できない「場」というものができているため、逸脱する、場合によっては出ていく覚悟がないと、踏み込んだ判断はできません。例えば福島原発事故の前にも、「もんじゅ」訴訟第二次控訴審と志賀2号炉原発訴訟で差し止めを認めた2人の裁判長がいましたが、ひとりは間もなく辞めて弁護士になっています。
神保 井戸(謙一)さんですね。
瀬木 高裁の裁判長のほうは、6年余りもの任期を残して辞められている。これは、僕はなぜなのか気になっています。こういうふうだから、自分が何のためにそう判断して、どんなポリシーで判決を出すのか、ということまで見えて、ある程度覚悟している、かなり意識の高い裁判官でないと思い切った判決は難しいでしょう。
裁判所や判決を監視、批判するマスメディアの役割
宮台 処方箋は単純です。ビジョンや見識を持てといっても駄目で、ビジョンや見識を持つことが不利になるようなコミュニケーション環境を変えるのです。先ほど申し上げた「内集団のための自己犠牲」ならぬ「包括集団(市民社会)のための自己犠牲」こそが徳ないし内発性になるような、育て方をするべきです。具体的に言えば、内集団の空気と違う行動をすれば内集団に座席がなくなりますが、それで孤独になって生きていけなくなるようなコミュニケーション環境さえ変えられれば、永続するポジション・トークから逃れられます。
神保 つまり、内集団以外にネットワークを持てと。
宮台 はい。この単純な処方箋が実行困難なのです。先ほど申し上げたように、家庭教育であれ学校教育であれ、親や教員はできるだけ異質な人間と出会わないように一生懸命です。同じ文化を持つ人たちが通う学校に入れたいなどと本気で考える頓馬が溢れているんですね。結婚相手を選ぶときも、家族文化が違うととにかく反対する馬鹿親。文化の違いを軽々と乗り越えるように子どもを育ててこなきゃいけなかった馬鹿親が悪い。この輩が、謂わば今日的な身分制度を支えているんです。
神保 制度もないのに、わざわざそうしていると。
宮台 子どもが悪いんじゃなく、むしろ良い子だからこそ馬鹿親に取り込まれ、社会の全体性が見えなくなります。こうした趨勢に抗う動きをどうやって組織するかが重要です。そのために僕は1年前から親業ワークショップを続けてきています。
確かに日本には近代的「公」、つまり市民社会のプラットフォームが未成熟です。でもそれを補う良心を育てられるはず。社会の多様性や流動性はマクロには増大するしかないから、多くの人は「見たくないものを見ない」ためのゾーニングに殺到します。でもそれでは偏見による排外主義の温床になりかねない。「見たくないものを見ることが社会の持続可能性につながる」「見たくないものを見よう、それが良心だ」と教育できるはず。でも87年に大学教員になって30年も定点観測してきたけど、学生たちはインターネットによる後押しもあって、ますます「見たくないものを見ない」方向に向かっている。結果、正義感が薄くなるか、ウヨ豚や糞リベみたいに内輪でしか通用しない妄想的正義にハマるか、どちらかです。
神保 トランプ現象的なものとも関係してくるかもしれませんね。「何を今どききれいごとを言っているのか」「おめでたい話をしている」ということになってしまう。瀬木先生、そうした議論も含め、司法についてどこから手を付ければいいでしょうか?
瀬木 行政は巨大な怪獣、ゴジラの死体のようなもので、どうやって始末したらいいかわからないし、どこを切っても放射能が出てきます。その点、司法はあまり権益がないので、マンモスの死体くらいで、まだなんとかなる。例えば、オランダやベルギーは大陸法系国で、本来はキャリアシステムなのですが、相当の割合で法曹一元にしています。そうでない場合でも、最低限、少しだけ弁護士をやるとか、ヨーロッパだと国によっては任用や昇進も裁判所から一定程度距離をとった委員会がやるということもある。せめて2~3割程度でもいいから、本当にすぐれた弁護士が、例えば6年から10年程度だけでも裁判官をやり、その人たちが自分の良心に従って働くということがあれば、風穴はあくから全然違ってくるでしょうね。
神保 人事を、もっと回すということですね。
瀬木 また、人事を透明性のあるものにすることも重要です。例えば委員会を作って人事を行い、自然と昇給するのではなく、同じランクの裁判官は同一給与にするとか、制度をいじろうと思えばいくらでもいじれる。しかし、そうしたことを主体的にやろうとする法律家がいるか、国民のコンセンサスや支援を得られるか、あるいはきちんと機能する委員会ができるか、という問題もあります。日本は法的、制度的リテラシーが、まだまだ低い。具体的な方策とともに、このリテラシーを長い目でよくしていく、ということの両方が必要だと思います。
宮台 今から2400年前、アリストテレスが『ニコマコス倫理学』で、罰に基づく秩序と、徳に基づく秩序を分けました。損得勘定の自発性と、内から湧く力としての内発性の区別です。似たことですが、真実についての知識と、真実の貫徹のための関与は、別です。社会哲学者ハーバーマスはそれを「認識と関心は別だ」と表現し、社会学者ルーマンは「言語と動機付け装置は別だ」と表現します。実は動機付け装置に注目するのが社会学の伝統です。
所属集団のために頑張るのは自己犠牲に見えますが、「座席を失いたくない」という動機は自己中心的な損得勘定です。同じ意味で、承認への要求も損得勘定です。「だから」日本人は世界中で一番自己中心的です。山岸俊男氏が多数の実験で確かめました。子どもに対して「勉強しないと負け組になるぞ」と損得勘定ばかり刺激する馬鹿親をどうやって取り除き、「なぜ立派な人間になろうとしないんだ」と昔みたいに言う親を増やす必要があります。
神保 今日は宿題がたくさん出ました。瀬木さん、最後にメディアについて伺います。今はメディアが判決や裁判所を批判することがタブーのようになっています。裁判所が中立・公正から外れているならメディアがそれを指摘しなければならないのに、あまりそれができていないように感じます。
瀬木 最近では、そこそこ報道が出るようになってきたと思います。雑誌、インターネットもそうだし、有力地方紙などもそう。ただマスになるほど、不文律というものは感じます。そこは、ジャーナリズムの名に値するように、批判すべきところは批判し、是々非々できちんと報道する姿勢を持ってもらいたい。民度が高くなって問題がよく見えるようになってきた部分もあるので、メディアもぜひそういう方向に沿って変わっていってほしいと思います。
(『マル激トーク・オン・ディマンド 第826回』を加筆、再構成して掲載)
(構成/橋川良寛・blueprint)
せぎ・ひろし
1954年愛知県生まれ。76年司法試験合格。77年東京大学法学部卒業。79年裁判官任官。東京地裁判事補、最高裁民事局付、大阪高裁判事、那覇地裁判事、最高裁調査官などを経て2012年退官。同年より現職。著書に『絶望の裁判所』(講談社現代新書)、『黒い巨塔 最高裁判所』(講談社)など。
神保哲生[ビデオジャーナリスト]
1961年生まれ。ビデオジャーナリスト。ビデオニュース・ドットコム代表。代表作に『ツバルー地球温暖化に沈む国』(春秋社)。近共著に『東海村・村長の「脱原発」論』(集英社新書)など。
宮台真司[社会学者]
1959年生まれ。首都大学東京教授。社会学者。代表作に『日本の難点』(幻冬舎新書)、『14歳からの社会学』(世界文化社)、『私たちはどこから来て、どこへ行くのか』(幻冬舎)など。
『マル激トーク・オン・ディマンド』とは
神保哲生と宮台真司が毎週ゲストを招いて、ひとつのテーマを徹底的に掘り下げるインターネットテレビ局「ビデオニュース・ドットコム」内のトーク番組。スポンサーに頼らない番組ゆえ、既存メディアでは扱いにくいテーマも積極的に取り上げ、各所からの評価は高い。(月額540円/税込)HP:http://www.videonews.com
人気記事ランキング
新・ニッポンの論点
- “分断の時代”に考える20年代の【共産主義と資本・自由主義】
- ロシアが社会主義国に見える理由
- 友好国だからこそぼったくる!「トランプ帝国主義」
- 全国紙も報じた終末論【2025年7月人類滅亡説】のトリセツ
- 世代を超えたカリスマ「SEEDA」の【アップデート&処世術】
- 『GQuuuuuuX』で変わる!? ガンダムの【IPビジネス新戦略】
- 教えて! 大﨑洋さん!! 逆風での船出「大阪万博」の愉しみ方
- パレスチナのジェノサイドと【日本の難民問題】の深層にあるもの
- さらば?芸能界のドン、【バーニング周防郁雄社長という聖域】
- [週刊誌記者匿名座談会]憶測と中傷び交う中居・フジ問題の論点
NEWS SOURCE
インタビュー
- 【沖 侑果】上京して間もなく1年、目標は「新しい友達を作る」!
- 【Miyauchi】彗星のごとく現れた〝今が大事〟な川崎の超スーパースター
- 【原つむぎ】グラビア界の至宝が、こだわりのボディメイクで作り上げた圧巻の肉体美
- 【中村正人×堤幸彦】夢を実現させる場所「渋谷 ドリカム シアター」プロジェクトが描く未来予想図
連載
- 【マルサの女】名取くるみ
- 【笹 公人×江森康之】念力事報
- 【ドクター苫米地】僕たちは洗脳されてるんですか?
- 【丸屋九兵衛】バンギン・ホモ・サピエンス
- 【井川意高】天上夜想曲
- 【神保哲生×宮台真司】マル激 TALK ON DEMAND
- 【萱野稔人】超・人間学
- 【韮原祐介】匠たちの育成哲学
- 【辛酸なめ子】佳子様偏愛採取録
- 【AmamiyaMaako】スタジオはいります
- 【Lee Seou】八面玲瓏として輝く物言う花
- 【町山智浩】映画でわかるアメリカがわかる
- 【雪村花鈴&山田かな】CYZOデジタル写真集シリーズ
- 【花くまゆうさく】カストリ漫報