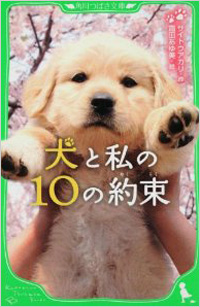虐待や惨殺も! 量産される危険な【動物映画】
──2012年には、年間でおよそ100本ほど発表されたという「動物映画」。そのコストパフォーマンスのよさによって製作ブームとなり、動物モデルのプロダクションの需要も高まっているという。しかし 、そんな映画の裏側で、動物たちにとっては“ほのぼの”してはいられない事情があるようで……。
『犬と私の10の約束』(角川つばさ文庫)
2011年頃から邦画業界で量産傾向にある「動物映画」。ヒットの目安とされる興行収入10億円を突破した作品といえば、近年では08年の『犬と私の10の約束』(15・2億円)が最後で、決してキラーコンテンツとは言い難い。しかし、動物をメインキャストに据えることで人件費が比較的抑えられ、また子どもから大人まで幅広い層の集客を見込めるため、不況のご時世でも費用対効果はそれなりに期待できる“安全牌ジャンル”として重宝されている。そうでなくても日本は震災以降、娯楽に“癒やし”や“絆”といった要素を強く求めるようになった節があり、往々にして愛らしい小動物と人、さらにその家族との絆が描かれる動物映画は、時流に乗ったジャンルともいえるだろう。
しかしながら、ここであえて疑問を呈したい。見る者に癒やしを与え、絆の大切さを教える動物映画……そう言い切ってしまって本当にいいのだろうか? 観客の目に届く動物たちの姿は、あくまで映画作品の中での“完成形”だ。人間の演者とは違い、言葉すら通じない動物たちがやすやすと指示通りに動けるはずがない。したがって、完成形に至るまで、動物たちは無理を強いられる羽目になる。その時点で「動物虐待」といえなくもないが、一般社団法人「国際どうぶつ映画協会」の事務局長を務める高野暢子氏いわく、「ひどい場合は演出のために殺してしまうこともある」という。
ログインして続きを読む
続きを読みたい方は...
Recommended by logly
人気記事ランキング
新・ニッポンの論点
- “分断の時代”に考える20年代の【共産主義と資本・自由主義】
- ロシアが社会主義国に見える理由
- 友好国だからこそぼったくる!「トランプ帝国主義」
- 全国紙も報じた終末論【2025年7月人類滅亡説】のトリセツ
- 世代を超えたカリスマ「SEEDA」の【アップデート&処世術】
- 『GQuuuuuuX』で変わる!? ガンダムの【IPビジネス新戦略】
- 教えて! 大﨑洋さん!! 逆風での船出「大阪万博」の愉しみ方
- パレスチナのジェノサイドと【日本の難民問題】の深層にあるもの
- さらば?芸能界のドン、【バーニング周防郁雄社長という聖域】
- [週刊誌記者匿名座談会]憶測と中傷び交う中居・フジ問題の論点
NEWS SOURCE
インタビュー
- 【沖 侑果】上京して間もなく1年、目標は「新しい友達を作る」!
- 【Miyauchi】彗星のごとく現れた〝今が大事〟な川崎の超スーパースター
- 【原つむぎ】グラビア界の至宝が、こだわりのボディメイクで作り上げた圧巻の肉体美
- 【中村正人×堤幸彦】夢を実現させる場所「渋谷 ドリカム シアター」プロジェクトが描く未来予想図
連載
- 【マルサの女】名取くるみ
- 【笹 公人×江森康之】念力事報
- 【ドクター苫米地】僕たちは洗脳されてるんですか?
- 【丸屋九兵衛】バンギン・ホモ・サピエンス
- 【井川意高】天上夜想曲
- 【神保哲生×宮台真司】マル激 TALK ON DEMAND
- 【萱野稔人】超・人間学
- 【韮原祐介】匠たちの育成哲学
- 【辛酸なめ子】佳子様偏愛採取録
- 【AmamiyaMaako】スタジオはいります
- 【Lee Seou】八面玲瓏として輝く物言う花
- 【町山智浩】映画でわかるアメリカがわかる
- 【雪村花鈴&山田かな】CYZOデジタル写真集シリーズ
- 【花くまゆうさく】カストリ漫報