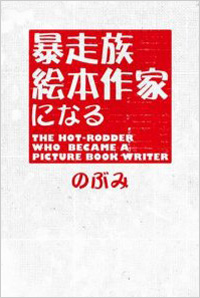──子どもが想像力の羽を広げる絵本。教育のツールにもなるそれは、健全な物語が描かれていなければならないし、我が子に役立つ教訓が説かれていなければならないと多くの親は思うだろう。だが、そんな世間一般のイメージを打ち破るヤバい絵本が、この世には存在するのだ。
『暴走族 絵本作家になる』(ワニブックス)
子どもの想像力をかき立てるべく親が読み聞かせる絵本は、健全な内容でなければいけない──。そんな暗黙のモラルがあるならば、あまりの恐ろしさに子どもがトラウマになるようにも思える絵本は、禁忌に抵触しているのか? 絵本作家養成の「あとさき塾」を共同主宰する編集者・小野明氏はこう話す。
「残酷さを一種のタブーと考えるなら、約150年ほどの近代絵本の歴史において、1847年に原書がドイツで刊行された『もじゃもじゃペーター』は古典的な名作として知られますが、かなり怖い。マッチで火遊びをする女の子が焼け死んだり、おしゃぶりの癖が治らない男の子が仕立て屋の巨大なハサミで指を切り落とされたり、子ども主体の残酷な10の小話が収録されています。また日本の恐い絵本の定番といえば、おばあさんを殺したタヌキを、ウサギがおじいさんに頼まれて仇討ちするという民話をベースにした『かちかちやま』。タヌキがおばあさんを殺して作った“ばば汁”を『このタヌキ汁、なんだかばぁさま臭くないか』とおじいさんが食べるくだりはゾッとする。この“ばば汁”の場面をはじめ数カ所が子どもには残酷だという理由で、現在は改作されたバージョンも多く流通しています。ただ、本作にはタヌキのような悪さをしたら懲らしめられるという教訓があるように、古くより絵本の中では子どもの“しつけ”のために怖い物語が描かれてきたのだと思います」
また違った怖さを追求した傑作として、米国の絵本作家エドワード・ゴーリーが61年に発表した『不幸な子供』を小野氏は挙げる。
「主人公は裕福な家に生まれた女の子ですが、火事や交通事故などあらゆる不幸が続き最終的に死ぬ、まったく救いようのない話。ゴーリーは残酷で不条理に満ちた作風で知られますが、ここまで徹底してダークな作品はほかにないと思う。しかしホラー映画/小説が存在するように、残酷さや不幸さを見たくなるのも人間の性にはあり、そうしたものをあくまで“虚構”として愉しむ方法を子どもに教え得る一冊のように思います」
そして恐怖絵本は、現在も生まれている。最近では、人気作家と画家/イラストレーターがコラボレーションした『怪談えほん』シリーズが2011年より刊行され、話題となった。児童文学の研究者・宮川健郎氏はこう述べる。
「学校の怪談などは子どもたちの語りと子どものための読み物として流布していましたが、怪談を絵本に落とし込んだ最初の例がこのシリーズといえます。特に怖がらせ方が異様なのが、作家の加門七海と画家の軽部武宏による『ちょうつがい きいきい』。主人公の男の子は、自室の扉のちょうつがいに挟まり“きいきい”と泣き叫ぶおばけを見つける。同様のちょうつがいが街のあちこちにあり、主人公と読み手はその音に精神的に追い込まれていきます。また宮部みゆきとイラストレーター・吉田尚令の『悪い本』は、心をもった“世界でいちばん悪い本”が読み手に“あなたは悪さをしたくなる”などと呪文のように語りかける。陰鬱な作品ですが、これを読んだ子どもは、自分を含めた誰の心にも“悪意”が潜んでいることに気づくかもしれません」
人気記事ランキング
新・ニッポンの論点
- “分断の時代”に考える20年代の【共産主義と資本・自由主義】
- ロシアが社会主義国に見える理由
- 友好国だからこそぼったくる!「トランプ帝国主義」
- 全国紙も報じた終末論【2025年7月人類滅亡説】のトリセツ
- 世代を超えたカリスマ「SEEDA」の【アップデート&処世術】
- 『GQuuuuuuX』で変わる!? ガンダムの【IPビジネス新戦略】
- 教えて! 大﨑洋さん!! 逆風での船出「大阪万博」の愉しみ方
- パレスチナのジェノサイドと【日本の難民問題】の深層にあるもの
- さらば?芸能界のドン、【バーニング周防郁雄社長という聖域】
- [週刊誌記者匿名座談会]憶測と中傷び交う中居・フジ問題の論点
NEWS SOURCE
インタビュー
- 【沖 侑果】上京して間もなく1年、目標は「新しい友達を作る」!
- 【Miyauchi】彗星のごとく現れた〝今が大事〟な川崎の超スーパースター
- 【原つむぎ】グラビア界の至宝が、こだわりのボディメイクで作り上げた圧巻の肉体美
- 【中村正人×堤幸彦】夢を実現させる場所「渋谷 ドリカム シアター」プロジェクトが描く未来予想図
連載
- 【マルサの女】名取くるみ
- 【笹 公人×江森康之】念力事報
- 【ドクター苫米地】僕たちは洗脳されてるんですか?
- 【丸屋九兵衛】バンギン・ホモ・サピエンス
- 【井川意高】天上夜想曲
- 【神保哲生×宮台真司】マル激 TALK ON DEMAND
- 【萱野稔人】超・人間学
- 【韮原祐介】匠たちの育成哲学
- 【辛酸なめ子】佳子様偏愛採取録
- 【AmamiyaMaako】スタジオはいります
- 【Lee Seou】八面玲瓏として輝く物言う花
- 【町山智浩】映画でわかるアメリカがわかる
- 【雪村花鈴&山田かな】CYZOデジタル写真集シリーズ
- 【花くまゆうさく】カストリ漫報